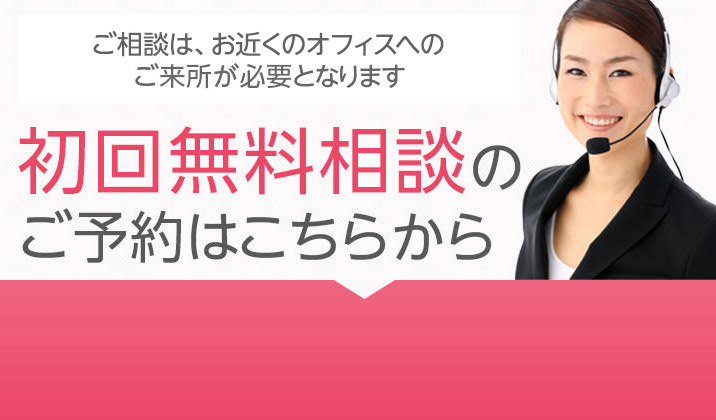保育費・学費の無償化は養育費の金額に影響ある?
- 養育費
- 養育費
- 無償化

鹿児島県が公表している統計によると、令和5年度の鹿児島市の出生数は4295名でした。鹿児島市に限らず、全国的に出生数は年々減少傾向にありますが、近年では少子化対策として、子どもの保育費や学費などが一部無償化されています。
保育費や学費の無償化により、子どもの養育に必要な費用が減った場合は、離婚後に授受する養育費の額にも影響するのでしょうか。本記事では、保育費や学費の無償化と離婚後の養育費の関係について、ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスの弁護士が解説します。
出典:「鹿児島県 統計情報 令和5年報」(鹿児島県)


1、少子化対策により無償化または減額された教育費等
近年では少子化が加速していることを踏まえて、子育て世代を経済的にサポートするため、子どもの保育費や学費の一部が無償化または減額されています。
以下より、無償化や減額の対象となっている、幼児教育・保育の費用、高等学校等の授業料、多子世帯の大学等授業料・入学金を紹介します。なお、申請前には、学校や各自治体に最新の支援情報を確認することをおすすめします。
-
(1)幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化(幼保無償化、保育無償化)は、令和元年10月からスタートしました。
幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)までのすべての子どもについて、利用料(保育料など)が無料になります。
また住民税非課税世帯では、0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもについても利用料が無料になります。認可外保育施設などについても、保育の必要性の認定を受ければ、一定額を上限として利用料が補助されます。
世帯収入や入園先などによりますが、毎月数万円程度の負担軽減となるため、家計にとっては大きな助けとなるでしょう。
参考:「幼児教育・保育の無償化」(こども家庭庁) -
(2)高等学校等就学支援金制度
平成26年4月以降に高等学校等へ入学する生徒については、所得要件(世帯年収約910万円未満)を満たす場合に限り、国公立学校の授業料相当額の支援金が支給されます。
また、私立学校に通う生徒についても、所得水準に応じて支援金が支給され、授業料が実質的に減額となります。
国公立高等学校等に通う生徒、および私立高等学校等に通う世帯年収約590万円以上910万未満の生徒については、年間11万8800円が支給されるため、月1万円程度の負担軽減となります。
私立高等学校等に通う世帯年収約590万円未満の生徒については、年間39万6000円が支給されるため、月3万円を超える負担軽減となります。
参考:「高等学校等就学支援金制度」(文部科学省) -
(3)多子世帯の大学等授業料・入学金の無償化・減額
文部科学省が令和2年4月から導入している「高等教育の修学支援新制度」の一環として、令和7年度から多子世帯の大学等授業料・入学金の無償化・減額支援制度が導入される予定です。
子ども3人以上の多子世帯における大学・短期大学・高等専門学校・専門学校(=大学等)の授業料・入学金が、無償化または減額されます。
無償化または減額支援の金額は、授業料年間70万円と入学金26万円です。所得制限はなく、学修意欲があれば幅広く利用できます。
ただし、出席率・修得単位数・成績評価によって定期的に学修意欲と学修成果が審査され、要件を満たせなければ支援打ち切りとなることがあります。
大学等に通う子ども1人当たり月6万円程度の負担軽減となるため、大学生年代の子どもを扶養している家庭にとっては大きな助けとなるでしょう。
参考:「高等教育の修学支援新制度」(文部科学省)
2、保育費・学費の無償化は、養育費に影響する?
保育費や学費の無償化または減額により、子どもを扶養するための費用が離婚当時の想定より少なくなった場合も、養育費の金額に影響を及ぼすことはないと解されています。
就学支援制度による就学支援金は、受給権者に支給されるものであり、権利者又は義務者の収入となるものではありません。
そして、その制度の趣旨が、高等教育等における教育にかかる経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与する点にあることを考慮し、子が就学支援機を受給していることをもって、養育費を減額すべきではありません。
-
(1)高校授業料無償化と養育費の関係が争われた裁判例|影響を及ぼさない
福岡高裁那覇支部平成22年9月29日決定の事案では、子どもが通う公立高等学校の授業料が無償化されたことに伴い、義務者である父親が婚姻費用の減額を求めました。
福岡高裁那覇支部は、以下の2点を理由として挙げ、高校授業料無償化は養育費の減額する方向に考慮すべきでないと判示しました。- 公立高等学校の授業料はそれほど高額でなく、子どもの教育費や母親世帯の生活費全体に占める割合もさほど高くないと推察されるため、授業料の無償化は婚姻費用を減額させるほどの影響を及ぼすものではない
- 高校授業料無償化を含む公的扶助等は、私的扶助を補助する性質のものであるため、婚姻費用の額を定めるに当たって考慮すべきものではない
最高裁も福岡高裁那覇支部の判断を是認したため、高校授業料無償化などの公的な支援措置による負担軽減は、養育費に影響を及ぼさないという解釈が定着しています。
- 公立高等学校の授業料はそれほど高額でなく、子どもの教育費や母親世帯の生活費全体に占める割合もさほど高くないと推察されるため、授業料の無償化は婚姻費用を減額させるほどの影響を及ぼすものではない
-
(2)父母が合意すれば、養育費を増減することは可能
保育費や学費の無償化を理由に、養育費の減額を求めても認められにくいです。しかし、父母が合意すれば、養育費の金額を増減することはできます。
養育費を一度取り決めた後でも、父母の収入バランスやその他の事情を考慮し、必要に応じて養育費の額を見直すことも選択肢の一つです。
お問い合わせください。
3、標準的な養育費の算定方法
標準的な養育費の金額は、父母の収入バランスや子どもの人数・年齢などによって決まります。個別の事情を考慮して金額を増減することは可能ですが、標準的な額を念頭に置きつつ交渉することが望ましいでしょう。
標準的な養育費の額は、以下の手順で計算します。なお、簡易的に養育費の額を計算したい方は、裁判所が公表している「養育費算定表」も適宜ご利用ください。
参考:「養育費・婚姻費用算定表」(裁判所)
-
(1)義務者と権利者の基礎収入を求める
まずは、義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の基礎収入を求めます。
基礎収入とは、総収入から子の養育費に充てるべきでない金額を控除したもので、以下の式によって計算します。基礎収入=総収入×基礎収入割合
【給与所得者】
総収入額(=源泉徴収票の支払金額) 基礎収入割合 0〜75万円 54% 〜100万円 50% 〜125万円 46% 〜175万円 44% 〜275万円 43% 〜525万円 42% 〜725万円 41% 〜1325万円 40% 〜1475万円 39% 〜2000万円 38%
【自営業者】
総収入額(=確定申告時の課税所得金額) 基礎収入割合 0〜66万円 61% 〜82万円 60% 〜98万円 59% 〜256万円 58% 〜349万円 57% 〜392万円 56% 〜496万円 55% 〜563万円 54% 〜784万円 53% 〜942万円 52% 〜1046万円 51% 〜1179万円 50% 〜1482万円 49% 〜1567万円 48%
たとえば、義務者の夫が給与所得者で年収500万円の場合、夫の基礎収入は210万円(=500万円×42%)です。
権利者の妻が給与所得者で年収200万円の場合、妻の基礎収入は86万円(=200万円×43%)です。 -
(2)子どもの生活費を求める
次に、子どもの生活費の金額を求めます。
子どもの生活費の計算式は、以下のとおりです。子の生活費=義務者の基礎収入×子の生活指数合計÷(義務者の生活指数(100)+子の生活指数合計)- 14歳以下の子:生活指数は1人当たり62
- 15歳以上の子:生活指数は1人当たり85
たとえば、義務者の夫が給与所得者で年収500万円の場合、夫の基礎収入は210万円です。
16歳と13歳の子どもが1人ずついるとすれば、子の生活費の額は「124万9798円」となります。子の生活費
=210万円×(85+62)÷(100+85+62)
≒124万9798円 -
(3)養育費の金額を計算する
最後に、以下の式によって養育費の額(年額)を計算します。
養育費=子の生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
たとえば、義務者の夫が給与所得者で年収500万円(基礎収入210万円)、権利者の妻が給与所得者で年収300万円(基礎収入800万円)で、16歳と13歳の子どもが1人ずついる場合(子の生活費124万9798円)、養育費の年額は「88万6681円」です。
月額に直すと「7万3890円」となります。養育費(年額)
=124万9798円×210万円÷(210万円+86万円)
≒88万6681円
養育費(月額)
88万6681円÷12
≒7万3890円
4、養育費の増額・減額が認められるケース
養育費を取り決めた後に以下のような事情変更が生じた場合には、養育費の増額または減額が認められることがあります。
- 権利者の収入が減った
- 義務者の収入が増えた
- 子どもに関する支出(学費や医療費など)が増えた
【養育費の減額が認められるケース】
- 義務者の収入が減った
- 権利者の収入が増えた
- 権利者の再婚相手が、子どもと養子縁組をした
- 義務者が再婚して子どもができた
養育費の増減に関する話し合いは、法的な観点から冷静に進めることが大切です。夫婦間での話し合いがまとまらないときは、お早めに弁護士へご相談ください。
5、まとめ
少子化対策の目的で導入されている保育費や学費の無償化は、原則として養育費の額に影響を及ぼしません。
しかし、養育費を取り決めた後の事情変更によって、金額を見直すべきケースはあります。養育費の増減について元配偶者と揉めてしまった場合は、弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。
ベリーベスト法律事務所は、養育費の増額や減額に関するご相談を随時受け付けております。養育費の増額や減額を求めたい方や、元配偶者から養育費の増額や減額を求められてお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています