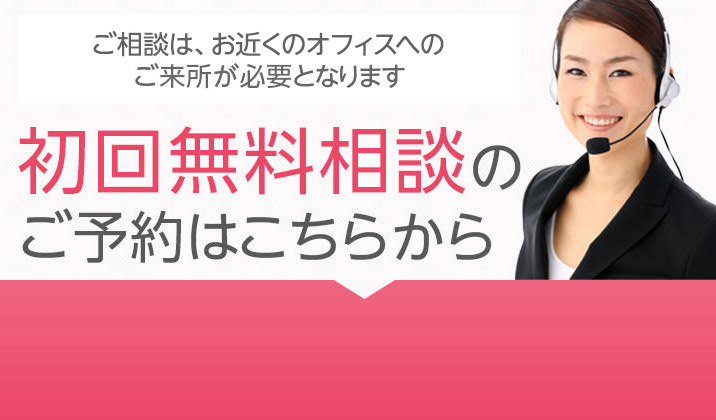養育費を払いながら再婚! 元配偶者への支払いは減額できる?
- 養育費
- 養育費
- 払いながら
- 再婚

鹿児島県が公表している統計資料によると、令和4年の鹿児島県内における男女の再婚件数は2442件でした。
再婚の際、前の配偶者との間に子どもがいる場合は、養育費の支払いを続けなければなりません。しかし、再婚をきっかけに経済状況の変化が生じたような場合には、養育費の減額が認められる可能性もあります。
今回は、養育費を払いながら再婚をする場合における養育費減額の可否とその方法について、ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスの弁護士が解説します。


1、養育費を払いながら再婚! 元配偶者への支払いはどうなる?
養育費とは、子どもが社会的・経済的に自立するまでに必要となる費用をいい、衣食住に必要な費用、教育費、医療費などが含まれます。
養育費は、親の子どもに対する扶養義務に基づいて支払い義務が発生します。そのため、再婚をしたとしても、子どもが社会的・経済的に自立するまでは養育費の支払い義務はなくなりません。
ただし、再婚をきっかけとして事情の変更があったと認められれば、養育費の「減額」が認められる可能性があります。
2、再婚によって養育費を減額できる可能性があるケース
再婚によって養育費を減額できる可能性があるケースとしては、以下の4つのケースが挙げられます。
-
(1)扶養する子どもが増えた
再婚相手との間に子どもが生まれた場合や再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合、扶養すべき子どもが増えることになります。
「元配偶者との間に生まれた子ども」「再婚相手の間に生まれた子ども」「養子縁組をした連れ子」、すべて扶養義務に関しての優先関係はありません。それぞれ同等の扶養義務が生じます。
そのため、扶養すべき子どもが増えると1人あたりにかけられる養育費が減りますので、養育費の減額事由となります。 -
(2)再婚した相手が無職、再婚相手を扶養した
再婚をすると養育費の支払い義務者は、再婚相手を扶養する義務が生じます。再婚相手が専業主婦(夫)であったり、怪我や病気で働けなかったりする状態だと、養育費の減額が認められる可能性があります。
ただし、再婚相手が無職であっても、健康で働ける状態であれば、養育費の減額事由として考慮されないケースもありますので注意が必要です。 -
(3)養育費を受け取る側が再婚し子どもが再婚相手の養子になった
養育費の支払いを受ける元配偶者が再婚した場合、再婚相手と子どもが養子縁組をすることがあります。
養子縁組をすると、再婚相手と子どもとの間には、法律上の親子関係が発生し、扶養義務が生じます。
この場合、実親と養親の双方が子どもに対して扶養義務を負うことになりますが、養親が一次的な扶養義務、実親が二次的な扶養義務となりますので、養育費の支払い義務者である実親は、元配偶者の再婚を理由として養育費の減額を請求することができます。 -
(4)再婚以外の理由として、支払う側・受け取る側の収入の変化
会社の業績悪化を理由にリストラされたり、勤めている会社が倒産したりするなどの理由で職を失い収入がなくなってしまうことがあります。
また、病気や怪我などで長期の入院になれば、その間働くことができませんので、同様に無収入になってしまいます。
このような事情により養育費の支払い義務者の収入が大幅に減少した場合は、減額が認められる可能性があります。
また、元配偶者が離婚時には無職であったものの、その後就職し、一定の収入を得るようになった場合には、養育費の権利者側の収入の増加を理由に、養育費の減額が認められる可能性もあります。
お問い合わせください。
3、養育費の減額を交渉したい場合の流れは?
養育費の減額を求める場合には、以下のような流れで行います。
以下、それぞれ解説します。
-
(1)元配偶者と交渉する
養育費の減額を希望するときは、まずは元配偶者との話し合いを行います。
元配偶者に連絡をとり、養育費を減額しなければならない事情が発生したことを丁寧に説明し、養育費の減額について理解を得られるよう努めましょう。
元配偶者との交渉で養育費の減額の合意がまとまったときは、変更内容をまとめた合意書を作成しておくようにしてください。
なお、当初の養育費の金額が調停や審判・裁判により決まったとしても、当事者間の合意により変更することができます。 -
(2)交渉がまとまらない場合は養育費減額調停を申し立てる
元配偶者との交渉では、養育費の減額についての合意が得られない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停の申立てを行います。
調停では、家庭裁判所の裁判官や調停委員が養育費の減額を求める理由や経緯、現在の収入などを確認した上で、問題の解決に向けた助言をしてくれます。養育費減額事由が認められる場合には、調停委員から元配偶者を説得してくれますので、当事者同士の交渉よりも話し合いがまとまる可能性が高いでしょう。
調停により合意がまとまったときは、その内容が調停調書にまとめられます。 -
(3)調停が不成立の場合、養育費減額審判で決定される
調停でも養育費減額の合意に至らないときは、最終的に養育減額審判により判断がなされます。
養育減額調停が不成立になると自動的に審判に移行しますので、特別な申立てを必要ありません。調停は、話し合いの手続きでしたが、審判では、裁判官が一切の事情を考慮して養育費の減額を認めるかどうか、減額後の養育費をいくらにするかを判断してくれます。
4、養育費減額調停を進める場合のポイント
当事者間で養育費減額の交渉がまとまらないときは、家庭裁判所に養育費減額調停の申立てる方法があります。以下では、養育費減額調停を進める際のポイントを説明します。
-
(1)現在の状況を踏まえて養育費を計算する
減額後の養育費の金額は、基本的には、養育費の権利者および義務者双方の収入と扶養義務のある子どもの人数に応じて決められます。
養育費の金額の相場は、裁判所が公表している養育費算定表により簡単に把握することができますので、まずは現在の状況を踏まえて養育費の相場を計算してみるとよいでしょう。
調停でも養育費の相場を前提とした金額で話し合いが進められますので、あらかじめ相場となる金額を把握しておけば、スムーズに話し合いができるでしょう。 -
(2)減額が正当であることを証明できるようにする
養育費は、当初定めた金額を支払うのが原則となりますので、養育費の減額を求めるには、2章で説明したような養育費の減額事由に該当する事情が必要になります。
調停では、養育費の減額を求める正当な理由があることを申立人の側で立証していかなければなりません。そのため、口頭での説明だけでなく、戸籍謄本、源泉徴収票、所得証明書など減額が正当であることを裏付ける証拠を準備しておくことが大切です。 -
(3)調停では感情的にならないようにする
調停では、調停委員を介して話し合いが進められますので、当事者同士が顔を合わせて話し合いをする必要はありません。そのため、当事者同士で交渉をするよりも冷静に話し合いを進めることができます。
もっとも、調停でもお互いの主張が対立すると、つい感情的になってしまい調停委員に強く当たってしまうことがあります。しかし、調停委員に感情的になっても決して交渉が有利になることはなく、むしろ調停委員を敵に回してしまうリスクがあります。
そのため、調停では、感情的にならないよう冷静に話をするよう努めましょう。 -
(4)弁護士に相談する
養育費の減額をしたいという場合は、自分だけで行動するのではなく、一度弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談をすることで、養育費の減額を請求できる事案なのかを判断してもらうことができ、減額後の養育費の相場も提示してもらえます。
自分で交渉する場合でも事前に弁護士のアドバイスがあれば、自信を持って話し合いを進めることができるでしょう。
また、自分で交渉や調停・審判をするのが不安だという方は、弁護士に依頼することで養育費減額請求の手続きを弁護士に任せることもできます。少しでも負担を軽減するためにも、弁護士への依頼を検討してみましょう。
5、まとめ
養育費を払いながら再婚すると、経済的に厳しいと感じることもあるでしょう。再婚により扶養家族が増えたり、収入に変化が生じたりした場合には、養育費を減額できる可能性があります。
ただし、話し合いでは互いになかなか合意できず、交渉、調停、審判により養育費の減額を求めていく可能性も十分にあり得るでしょう。
養育費の再計算や相手との交渉が不安な方は、まずはベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスまでお気軽にご相談ください。離婚・男女問題の実績がある弁護士が状況を伺い、解決に向けてサポートいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています