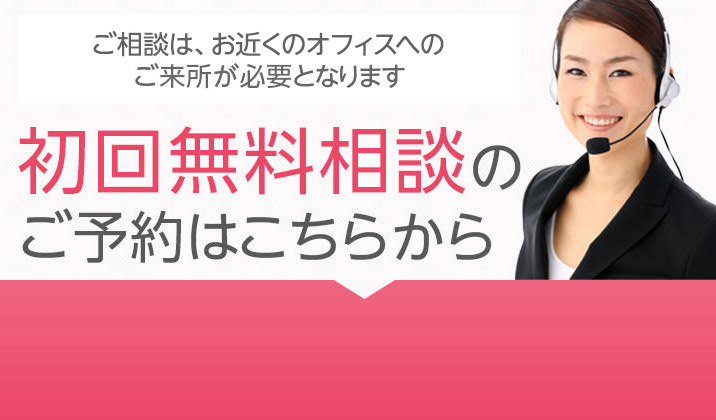婚姻費用を払わなくていい場合はある? 支払い義務とリスク
- その他
- 婚姻費用
- 払わなくていい場合

鹿児島県の発表している「人口動態統計」によると、令和4年に鹿児島県では2455組の夫婦の離婚が成立しました。
離婚する夫婦の中には、離婚前から別居をするという夫婦も少なくありません。「DVから逃げるため」や「不倫をした相手と一緒にいたくないから」など、別居の理由はさまざまですが、ここで重要になってくるのが「別居後の婚姻費用が払われるか?」です。
ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスの弁護士が、婚姻費用の支払い義務について詳しく解説していきます。


1、婚姻費用を払わなくていい場合はある? 支払い義務とは
そもそも婚姻費用の支払い義務とはどういうものなのでしょうか?
婚姻費用の支払い義務とは何か、婚姻費用を支払わなくてもいいケースはあるのかどうか、みていきましょう。
-
(1)婚姻費用の支払い義務とは
民法760条には「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定されていますが、その義務は別居後もなくなりません。
そのため、収入差がある夫婦の場合、収入の多い方が収入の少ない方に対して、婚姻生活を維持するための必要費用である「婚姻費用」を支払う義務があるのです。
なお、婚姻費用には以下の費用が含まれます。- 夫婦の衣食住の費用
- 出産費
- 医療費
- 子の監護に要する費用
- 教育費
- 葬祭費
- 交際費
婚姻費用の支払期間は、婚姻費用を請求した時から、離婚成立あるいは別居を解消して再び同居するまでの間です。
-
(2)婚姻費用を支払わなくてもいいケース
婚姻費用を支払わなくてもいい、あるいは減額になる可能性があるのは、配偶者が有責配偶者に当たる場合です。
有責行為に及ぶなど、別居ないし婚姻関係の破綻につき専ら又は主として責任がある配偶者のことを「有責配偶者」といいます。
そして、有責行為とは、類型的に婚姻関係の破綻を招くような他方配偶者の責めに帰すべき行為を言います。
具体例としては、具体的離婚原因としても規定される不貞行為(民法770条1項1号)、悪意の遺棄(民法770条1項2号)のほか、暴力、重大な侮辱、不労、浪費、犯罪行為等が挙げられます。
有責配偶者からの婚姻費用分担請求権は、信義則あるいは権利濫用の見地から、子の生活費に関わる部分に限って認められます。
有責性については、夫から、妻が無断で家を出たことをもって、妻に責任がある旨の主張が多いです。
確かに、配偶者には、同居義務があるため(民法752条)、正当な理由なく別居すれば、同居義務違反となります。しかし、婚姻関係が既に破綻している場合や別居の原因を他方配偶者が作っている場合などは、別居に正当な理由があるとされます。
そのため、配偶者が一方的に住居から出て行ったとの外形的事実だけでは、これを有責ということはできません。
2、婚姻費用を支払わない3つのリスク
相手が有責配偶者のようなケース以外で婚姻費用を支払わないことは、さまざまなリスクがある行為です。
婚姻費用を支払わない場合の3つのリスクについて、詳しくみていきましょう。
-
(1)離婚時に不利になる
婚姻費用を支払わない場合、離婚時に不利になる可能性があります。
まず、民法は、「悪意の遺棄」を具体的離婚原因としています(民法770条1項2号)。そして、「悪意の遺棄」とは、婚姻共同生活の廃絶を意図して、配偶者との同居・協力・扶助義務(民法752条)又は婚姻費用分担義務(民法760条)に違反する行為をいいます。
そのため、婚姻費用を支払わないという行為は、「悪意の遺棄」に当たるとみなされる可能性があります。
「悪意の遺棄」に当たるとみなされた場合は、ご自身が有責行為を働いたとして慰謝料請求を受けるなど、離婚時に不利になるおそれがあるでしょう。 -
(2)調停を申し立てられる
婚姻費用を支払わない場合、相手から「婚姻費用分担調停(婚姻費用分担請求調停)」を申し立てられる可能性があります。
婚姻費用分担調停の内容は後述しますが、この調停で婚姻費用について合意したにもかかわらず支払わなかった場合は、相手からの申し出によって裁判所から「履行勧告」や「履行命令」を受ける可能性があるのです。
「履行勧告」は「婚姻費用を支払うように」という催促にとどまるため、法的拘束力はありません。一方、「履行命令」に従わない場合、10万円以下の罰金(過料)を課される可能性があるでしょう。 -
(3)差し押さえを受ける
婚姻費用について取り決めた通りに支払わなかった場合や、履行勧告・履行命令を無視した場合、「強制執行」によって給料や預貯金を差し押さえられる可能性があります。
給料が差し押さえられる場合は、裁判所から会社に通知が送られてくることで婚姻費用を支払っていないことが会社にばれてしまい、居づらくなってしまうケースもあるでしょう。まずはお気軽に
お問い合わせください。メールでのお問い合わせ営業時間外はメールでお問い合わせください。
3、婚姻費用はどのようにして決める?
婚姻費用はどのようにして決めるのでしょうか?
婚姻費用の決め方についてみていきましょう。
-
(1)夫婦間での話し合い
まずは以下の流れで婚姻費用について決めていきます。
① 婚姻費用の金額を決める
家庭裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考に決めるのが一般的です。
② 公正証書の作成
婚姻費用の金額や支払い方法などが決まった場合、「公正証書」を作成することが望ましいといえます。
「公正証書」は、公証役場で公証人に作成してもらうことができる公文書です。
公正証書を作成していないと、たとえば「婚姻費用は毎月5万円支払う」と合意したにも関わらず、相手がその支払義務を履行しなかったとき、相手に対して強制執行ができなくなってしまいます。 -
(2)婚姻費用の分担請求調停
夫婦間の話し合いで決まらなかった場合、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。
調停は、調停委員2人と裁判官1人から構成される「調停委員会」に仲介してもらいながら、話し合いで争いを解決するための制度です。調停委員からアドバイスを受けたり、和解案を提示されたりしながら話し合いを進めていきますが、1回の話し合いで終わるケースはほとんどありません。
何度か調停で話し合い、合意を目指します。婚姻費用について合意に至れば「婚姻費用分担請求調停」は成立です。 -
(3)婚姻費用分担請求審判
調停で合意に至らず不成立になった場合、自動的に「婚姻費用分担請求審判」に移行します。
審判では、当事者の主張や、提出された資料・証拠を元に、裁判官が婚姻費用の分担についての審判を下されるため、婚姻費用が免除・減額になるケースは、相手の有責の証拠を用意しておくことが重要です。
4、婚姻費用に関するトラブルは弁護士へ
婚姻費用に関するトラブルは弁護士へ相談することがおすすめです。
弁護士が依頼者に代わり相手と交渉することで、調停や審判になる前に解決できる可能性が高まります。また、減額・免除に該当するケースにおいて、調停や審判になった場合に提出できる有効な証拠の集め方に関してアドバイスを受けることも可能です。
さらに、公正証書の作成手続きや、「婚姻費用分担請求調停」や「離婚調停」といった裁判手続きなども一任することができます。
調停や審判に進む前に話し合いの段階で解決できた方が、時間も費用もかからないため、早期の解決のためにもなるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
5、まとめ
婚姻費用は原則支払わなければなりません。しかし、配偶者が有責配偶者の場合など、減額や免除か認められるケースもあります。
婚姻費用を支払わないでいると、「離婚時に不利になる」「調停を申し立てられる」「差し押さえを受ける」といったリスクもあるため、婚姻費用に関する話し合いは必ず行いましょう。
婚姻費用について話し合いで解決できない場合は調停・審判に進み、その分費用や解決までの時間がかかってしまいます。
早期解決のためには、早い段階で弁護士に相談することが大切です。ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスでは、離婚問題の解決実績がある弁護士が在籍しています。まずはお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|