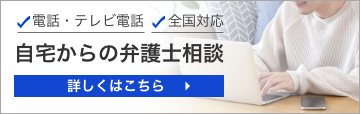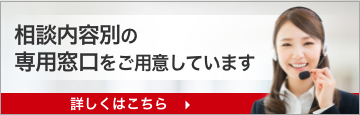姻族関係終了届とは|配偶者の死後に義実家と縁を切るときに必要な届け
- 一般民事
- 姻族関係終了届

配偶者が亡くなったとしても、それだけでは義理の両親との法的関係が解消されるわけではありません。義理の両親や義理の兄弟姉妹との関係を法的に解消するためには、「姻族関係終了届」を提出する必要があります。
義理の両親との折り合いが芳しくない場合には姻族関係終了届の提出を検討することになりますが、姻族関係を終了するとさまざまな影響が生じるため、手続きを行う前にしっかりと検討することが大切です。
本コラムでは、姻族関係終了届の概要やメリット・デメリットなどについて、ベリーベスト法律事務 所鹿児島オフィスの弁護士が解説します。
1、姻族関係終了届とは
まず、姻族関係終了届に関する基本事項について説明します。
-
(1)姻族関係終了届とは?
姻族とは、婚姻によって発生する親族のことをいいます。
配偶者と婚姻することによって、配偶者の父母や祖父母、兄弟姉妹などが姻族になり、法律上3親等内の姻族は親族と扱われます(民法725条3号)。
姻族関係終了届は、このような婚姻で発生した姻族関係を終了させるための届け出です。
夫婦が離婚をすれば義理の両親との姻族関係も解消されますが、配偶者と死別した場合には、当然には姻族関係は終了しません。
そのため、「配偶者と死別後に配偶者の血族との縁を切りたい」という場合には姻族関係終了届を提出する必要があるのです。 -
(2)姻族関係終了届による影響とは?
以下では、姻族関係終了届を提出することで生じる影響を解説します。
- ① 姻族関係終了届を出したときの子どもへの影響
亡くなった配偶者との間に子どもがいる場合には、姻族関係終了届を提出したとしても、子どもへの影響はありません。
子どもは、亡くなった配偶者の親族との関係では「血族」にあたるため、姻族関係が終了したとしても血族である地位に影響は生じないのです。
配偶者自身は姻族関係終了届によって亡くなった配偶者の親族との縁を切ることができますが、子どもについては、親族との関係を完全に絶つことは難しいといえます。 - ② 戸籍との関係性
配偶者が死亡すると、亡くなった配偶者は戸籍から除外されます。
その後、姻族関係終了届が受理されると、戸籍の身分事項の欄に「親族との姻族関係終了届出」との記載がなされて、姻族関係が終了したことが戸籍上明記されます。
なお、姻族関係終了届によって、戸籍が異動になったり、姓が変わったりすることはありません。 - ③ 相続への影響
姻族関係終了届によって亡くなった配偶者の親族との縁が切れることになりますが、亡くなった配偶者の相続人であるという地位には、影響は生じません。
そのため、姻族関係終了届を提出したとしても、亡くなった配偶者の遺産を相続することができるほか、すでに相続した遺産を返還する必要もないのです。
- ① 姻族関係終了届を出したときの子どもへの影響
2、姻族関係終了届の効果
以下では、姻族関係終了届によって生じる効果を解説します。
-
(1)扶養義務の消滅
民法では、直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があるとされています(民法877条1項)。
姻族は直系血族ではありませんので、法律上の扶養義務はありませんが、特別な事情がある場合には、家庭裁判所は、3親等内の親族間でも扶養義務を生じさせることができるとされています(民法877条2項)。
そのため、姻族としての地位が残っていると、家庭裁判所の審判により扶養義務を課せられるおそれがあるのです。
しかし、姻族関係終了届により姻族関係が終了すれば、将来扶養義務が課せられるおそれはなくなります。 -
(2)同居による互助義務の消滅
民法では、直系血族および同居の親族は、互いに助け合わなければならないとされています(民法730条)。
配偶者の死亡後も配偶者の親族と同居している場合には、法律上の互助義務が発生します。
同居の解消により互助義務を解消できますが、事情により同居を解消できない場合には、姻族関係終了届によって、互助義務を消滅させることができます。 -
(3)祭祀承継者を回避することができる
祭祀(さいし)承継者とは、系譜、祭具、墳墓など先祖代々受け継がれている祭祀財産を承継して、祖先の祭祀を主宰する人のことをいいます。
配偶者が死亡して祭祀承継者になってしまうと、お墓や仏壇を管理したり、法事を開催したりするなどの手間が生じます。
しかし、姻族関係終了届によって配偶者の家族とは無関係になるので、亡くなった配偶者の家族に祭祀承継者を引き継いでもらうことができるのです。
3、姻族関係終了届を出すメリット・デメリット
以下では、姻族関係終了届を出すことのメリットとデメリットを解説します。
-
(1)姻族関係終了届を出すことのメリット
姻族関係終了届を出すことには、以下のようなメリットがあります。
- ① 配偶者の親族との縁を切ることができる
配偶者の生前から義理の両親との関係が芳しくなかった場合、配偶者が亡くなったことによって間に入ってくれる人がいなくなりますので、関係がさらに悪化する可能性があります。
姻族関係終了届によって、亡くなった配偶者の親族との関係を法的に解消することができますので、今後の付き合いから生じるストレスを解消することができるでしょう。 - ② 相続への影響は生じない
姻族関係終了届を提出したとしても、相続への影響は生じませんので、亡くなった配偶者の遺産を相続することができます。
亡くなった配偶者の遺族から遺産を返すように要求されたとしても、それに従う必要はありません。
離婚をした場合は配偶者との関係も解消されてしまうため、配偶者の遺産を相続することができなくなります。 しかし、姻族関係終了届であれば、姻族との関係のみ終了させることができるため、配偶者の遺産を相続できるというメリットがあるのです。 - ③ 遺族年金を受給できる
配偶者が亡くなった場合には、残された遺族は、遺族年金の支給要件を満たしていれば遺族年金を受給することができます。
姻族関係終了届を提出したとしても、遺族年金を受給したり、これまでに受給していた遺族年金を引き続き受給することができます。
- ① 配偶者の親族との縁を切ることができる
-
(2)姻族関係終了届を出すことのデメリット
姻族関係終了届を出すことには、以下のようなデメリットがあります。
- ① 姻族関係終了を撤回できない
いったん姻族関係の終了という効果が生じてしまうと、後日に「姻族関係を復活させたい」と思っても、姻族関係の終了を撤回できません。
そのため、姻族関係を終了させるかどうかは、慎重に判断する必要があります。 姻族関係の終了によって扶養義務や互助義務は消滅しますが、そのことは、扶養や互助を受ける権利が消滅することも意味します。
つまり、将来に経済的な援助が必要になったとしても、義理の両親を頼ることができなくなってしまうのです。
一時的な感情に任せて姻族関係を終了するのではなく、将来の影響や今後の経済的な展望も考慮したうえで判断しましょう。 - ② 子どもと姻族との関係は切れない
姻族関係終了届により解消できるのは、配偶者の親族との姻族関係のみです。
亡くなった配偶者との間に子どもがいる場合は、配偶者の親族との関係では血族であるため、姻族関係終了によっても関係を切ることができません。
子どもの誕生日や入学・卒業などのライフイベント、姻族の死亡による葬儀・法要などでは、関係を解消したはずの姻族と顔を合わせる機会もあるかもしれません。
姻族関係終了届を提出していると、そのような機会に気まずい思いを抱いてしまう可能性もあります。
- ① 姻族関係終了を撤回できない
4、姻族関係終了届の提出方法
以下では、姻族関係終了届を提出する方法を解説します。
-
(1)姻族関係終了届を提出できる人
姻族関係終了届を提出できるのは、配偶者と死別した生存配偶者に限られます。
また、姻族関係終了届の提出にあたって死別した配偶者の血族の同意は必要ないため、生存配偶者が自らの意思で決定することができます。 -
(2)姻族関係終了届の提出先
姻族関係終了届は、本籍地またはお住まいの市区町村役場の窓口に提出してください。
また、大規模な自治体では支所や出張所などが設けられていることがありますが、そのような場所にも提出することができます。 -
(3)必要書類
姻族関係終了届を提出する際には、以下のような書類が必要になります。
- 姻族関係終了届
- 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場に提出する場合)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑
-
(4)姻族関係終了届の提出のタイミング
姻族関係終了届は、配偶者の死亡届を提出後であれば、いつでも提出することができます。
提出に期限はありませんので、ご自身の都合のよいタイミングで提出しましょう。
5、まとめ
配偶者と死別した場合、姻族関係終了届によって、死別した配偶者の血族との関係を解消することができます。
そして、姻族関係終了届を提出したとしても、死別した配偶者の遺産を相続することができ、遺族年金を受給することもできます。
死別した配偶者親族との関係が芳しくない場合には、姻族関係終了届を検討してみましょう。
もし、亡くなった配偶者の遺産をめぐって義理の両親や義理の兄弟姉妹と相続に関するもめ事が発生したり、その他の親族トラブルが発生したりした姻族関係終了届場合には、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています