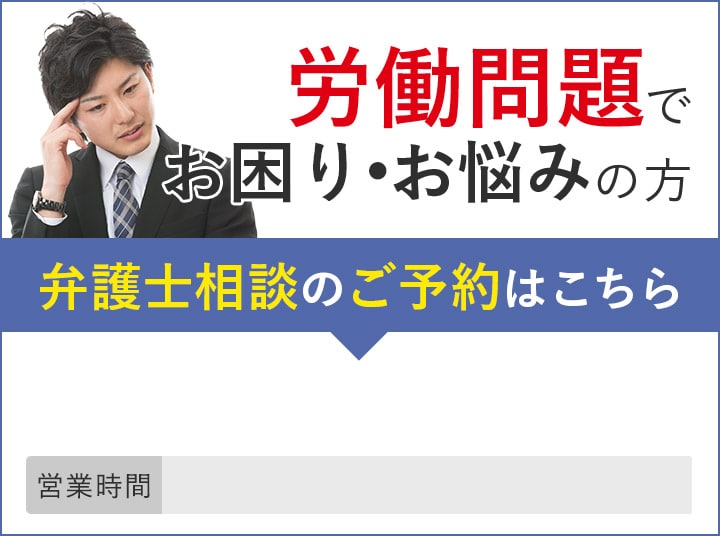退職するとボーナス減額はどのくらい? 対処法を弁護士が解説
- その他
- 退職
- ボーナス減額
- どのくらい

退職を検討中の方の中には、「ボーナスをもらってから退職したい」と考えている方もいると思います。しかし、会社の就業規則の定めによっては、退職予定の人は、ボーナス減額がなされる場合があります。
どのくらい減額されるかはケースバイケースですが、2割程度減額される可能性もあるため、辞めるタイミングは慎重に見極める必要があります。
今回は、退職するとボーナス減額はどのくらいになるのか、ボーナスが不当に減額された場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスの弁護士が解説します。


1、退職するとボーナスはどのくらい減額される?
退職するとボーナスはどのくらい減額されてしまうのでしょうか。退職時のボーナス減額について、ボーナスの支給義務の有無、一般的な減額の範囲、年俸制の場合の特徴など、主要なポイントを解説します。
-
(1)そもそもボーナスの支給は義務ではない
まず、ボーナス(賞与)は、通常、年に2回(夏季、冬季)または1回(前年度分を翌2~3月に支給)で、当該企業の業績配分、賃金後払い的性格を有するものです。
ボーナスを減額されると「違法ではないか」と考える人もいると思います。
しかし、賞与(ボーナス)制度は任意の制度であり(労働基準法89条4号)、その設計は当該企業の裁量の問題であって、労働者に当然に賞与請求権が認められるものではありません。
そのため、ボーナスを支給しないまたはボーナスを減額するという措置をとられたとしても、直ちに違法になるわけではありません。 -
(2)退職予定の従業員に対するボーナスは2割程度減額される可能性がある
ボーナスには、仕事の成果に対する評価という要素だけでなく、今後も引き続き勤務してくれる従業員のモチベーションアップを図り、活躍の期待を込めて支払われる性質があります。そのため、退職を予定している従業員に対しては、会社の規定に基づいて、ボーナスから一定程度減額することがあるのです。
退職予定者に対するボーナス減額が争点になった裁判例(東京地裁平成8年6月28日判決)では、ボーナス支給後すぐに退職した労働者に対して、会社が賞与規程に基づき、ボーナスの8割カットを求めたところ、裁判所は、これを認めず約2割の程度でしか減額を認めませんでした。
そのため、退職によりボーナスが減額される可能性はあるものの、その額は2割程度にとどまると考えられるでしょう。
2、退職した際にボーナスを減額された場合の対処法
退職時にボーナスを不当に減額されてしまった場合は、以下のような対処法を検討してみましょう。
-
(1)就業規則の支給条件を確認する
ボーナスの支給は、法律上の義務ではありませんので、ボーナスを支給するかどうか、どのくらい支給するのか、退職時に減額されるのかなどの条件については会社が自由に決めることができます。
ボーナスが支給されている会社では、一般的に就業規則にボーナスの支給条件などについての定めがありますので、まずは就業規則を確認してみましょう。
就業規則に退職を理由としてボーナスを減額するという内容の項目がなければ、会社によるボーナスの減額は違法になる可能性がありますので、それを理由に争っていくことができます。 -
(2)減額の理由を会社側に問い合わせる
就業規則の確認とともに、ボーナス減額の理由を会社に問い合わせてみてもよいでしょう。
会社側からボーナス減額の理由がきちんと説明されないようであれば、恣意的な減額である可能性もあります。
どのような理由でボーナス減額をしたかは、今後会社と争っていくための重要な証拠になりますので、口頭での回答だけではなく、必ず書面による回答を求めるようにしましょう。 -
(3)弁護士に相談する
就業規則の支給条件の確認や会社への減額理由の問い合わせをしてもボーナス減額に納得ができないときは、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は法的観点からボーナス減額の違法性を判断できるので、違法なボーナス減額がなされているようであれば、会社に対して、減額されたボーナスの支給を求めていくことができます。
また、就業規則にボーナス減額の根拠があったとしても、2割以上の減額をされているようであれば違法・不当なボーナス減額にあたる可能性があります。
どのくらいの減額が適正であるかは、事案によって異なりますので、この点についても専門家である弁護士に判断を依頼した方がよいでしょう。
また、ボーナスの請求権は、原則として3年の時効があります。時効を迎えると支払い請求ができなくなるため、早めに対応することが重要です。
お問い合わせください。
3、会社に退職を伝える前に知っておくべきこと
退職の際は報酬や業務の面でトラブルになることがあるため、事前に対策をして、できるだけもめずに退職をすることが望ましいでしょう。会社に退職を伝える場合にあらかじめ知っておくべきポイントとしては、以下のようなことが挙げられます。
-
(1)業務の引き継ぎ期間を設けて退職日を決める
会社を退職する場合には、後任者への業務の引き継ぎが必要になります。引き継ぎが不十分なまま退職をしてしまうと、会社や同僚に迷惑をかけることになる上に、「ボーナスのもらい逃げ」という印象を持たれてしまいます。
そのため、十分な引き継ぎ期間を設けるためにも、退職日から逆算して退職を伝える日を決めるようにしましょう。
一般的には引き継ぎ期間として1か月程度は必要になりますので、有給消化を予定している場合には、余裕をもった引き継ぎ期間を設定するようにしてください。 -
(2)ボーナスが支給された後に退職を申し出る
会社の就業規則によっては、ボーナスの支給に関して「支給日在籍要件」が設けられているところもあります。
支給日在籍要件とは、ボーナスの支給日に在籍している従業員に対してのみボーナスを支給するという制度です。支給日在籍要件が設けられている場合、ボーナスが支給される前に退職をしてしまうとボーナスの支給を受けることができません。
そのため、退職をするタイミングは、ボーナスが支給された後の方がよいでしょう。
ただし、ボーナス支給直後に退職の申し出をするとあまりよい印象を持たれませんので、円満に退職するのであればある程度の期間を空けて退職を伝えるようにしてください。 -
(3)未払い残業代がないか確認する
退職する際には、未払いの残業代がないかどうかを確認することも大切です。
会社に在籍中は、会社との関係性の悪化を危惧して、未払い残業代があったとしても請求せずにいたかもしれませんが、退職のタイミングであればそのような心配はありませんので、これまでの未払い分をしっかりと請求していくようにしてください。
ただし、残業代には、残業代の発生時期に応じて以下のような時効があります。- 残業代の発生が令和2年3月31日以前である場合:時効期間は2年
- 残業代の発生が令和2年4月1日以降である場合:時効期間は3年
残業代が時効になってしまってからでは会社に請求するのは困難ですので、残業代請求を考えている場合には、早めに行動することが大切です。
4、労働トラブルは弁護士に相談を
退職を理由にボーナスの支給額が不当に減額されてしまったなど、会社との労働トラブルでお困りの方は、弁護士に相談することをおすすめします。
-
(1)会社との交渉を任せられる
ボーナス減額や未払い残業代の請求など会社との間でトラブルが生じると、まずは会社との話し合いによりトラブルの解決を目指していくことになります。
しかし、労働者個人の力では会社と相手に自分の主張を認めてもらうのは困難ですので、弁護士によるサポートを受けた方がよいでしょう。弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として会社と交渉することができますので、労働者側の主張を認めてもらえる可能性が高くなります。
自分で対応するのが難しいと感じたときは、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。 -
(2)ボーナスの減額が問題ないか法的に判断ができる
ボーナス減額が違法性を判断するには、法的知識や経験が不可欠となりますので、労働者個人では正確に判断することが難しいといえます。
ボーナス減額が違法であれば会社に対して減額された分の支払いを請求することができます。不当に奪われたボーナスを取り返すためにもまずは弁護士に相談するようにしましょう。 -
(3)未払い残業代請求や裁判などの手続きに対応できる
退職の際に未払い残業代を請求するケースも多いですが、会社が未払い残業代の支払いに応じてくれない場合は、労働審判や裁判などの法的手続きが必要になります。
弁護士に依頼をすれば会社との交渉だけではなく、労働審判や裁判などの法的手続きにも対応してもらうことができます。
交渉とは異なり労働審判や裁判などは知識や経験がなければ対応が難しい手続きですので、専門家である弁護士に任せた方が安心です。
5、まとめ
ボーナス支給は義務ではないため、退職予定の場合、2割程度減額されてしまう可能性があります。
ただし、ボーナス減額は会社が自由に行うことができるわけではなく、就業規則などの根拠が必要になりますので、退職を理由にボーナスを減らされた場合は就業規則の確認などの対応が必要です。
未払い残業代の請求など、労働トラブルでお悩みの方はベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています